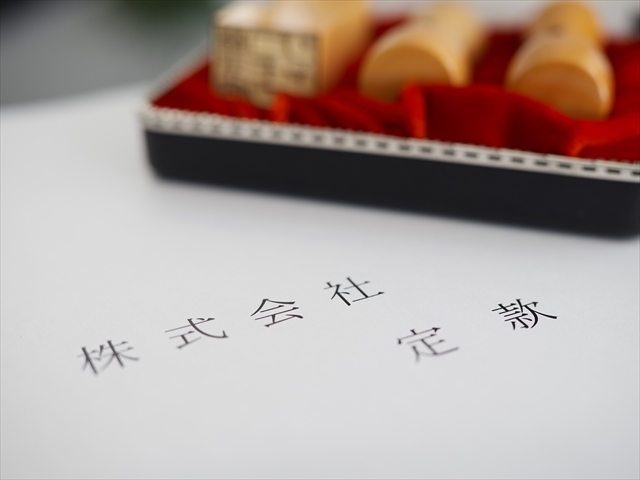タオバオ仕入れで事業を始めたい?会社設立の流れを完全解説!手続きから営業開始までの全プロセス
会社を設立することは、新しい事業をスタートさせるための大きな一歩です。
しかし、初めての会社設立には、何から始めればよいのか、どのような手続きが必要なのか、戸惑うことも多いのではないでしょうか。
本記事では、会社設立の基本的な手順をわかりやすく解説します。事業計画の作成から設立登記、営業開始に至るまで、各ステップでのポ
イントや注意事項を丁寧にご紹介します。
1はじめに
1.1会社設立の目的とメリット
会社を設立する目的は人それぞれですが、多くの場合、自身のビジネスを正式な形で展開し、信頼性や事業の拡大を目指すことにあり
ます。
法人化することで、個人事業主では得られないさまざまなメリットを享受できます。
まず、会社を設立することで信用力が向上します。
法人名義で契約や取引を行うことで、取引先や顧客からの信頼を得やすくなり、大口取引や長期契約の締結ができるようになります。
さらに、法人化することで資金調達の幅が広がる点も大きなメリットです。金融機関からの融資が受けやすくなり、事業拡大のための
資金を確保しやすくなります。
また、法人では節税効果を期待できる場合もあります。
給与所得控除や経費計上の幅が広がり、適切な経理処理を行うことで、税負担を軽減できる可能性があります。
さらに、法人を設立することで個人と会社の責任を分離できるため、万が一の事業リスクから個人資産を守ることができる点も見逃せ
ません。
1.2主な会社形態(株式会社、合同会社など)の違い
会社を設立する際に、どの会社形態を選ぶかは大事なポイントです。日本で一般的な会社形態には、株式会社と合同会社があります。
それぞれに特徴があるため、事業内容や規模に応じて適切な形態を選びましょう。
●株式会社
株式会社は、日本で最も一般的な会社形態です。
その特徴は、資本金を株式として分割し、株主が出資者となる点にあります。
株主は出資額に応じて議決権を持ち、取締役が会社を経営します。
株式会社の主なメリットは、信用力が高いことです。
多くの企業や取引先にとって、株式会社は信頼できる法人形態とみなされるため、大規模な取引や外部資金の調達に向いています。
一方で、設立費用や運営コストが高めであること、定期的な株主総会の開催や決算公告などの法的義務があることがデメリットとして
挙げられます。
●合同会社
合同会社は、2006年に新たに導入された比較的新しい会社形態です。
特徴は、出資者が経営者となり、柔軟な運営ができる点にあります。
取締役会や株主総会の開催義務がなく、経営方針を出資者間で自由に決定できるため、シンプルで効率的な経営が可能です。
また、設立費用が株式会社よりも低く、維持コストも抑えられるため、個人事業主が法人化を検討する際に選ばれることが多い形態で
す。
ただし、株式会社と比べると知名度が低いため、大規模な取引や資金調達においては信用力の面で劣る場合があります。
そのため、事業規模が小さい場合や、家族経営のような小規模事業に適しています。
2ステップ1:事業計画と基本事項の決定
事業計画の中心となるのが、事業内容の定義です。どのような商品やサービスを行うのか、そしてその価値を誰に届けるのかを具体的に明確化しましょう。
2.1事業内容とターゲットの明確化
事業内容を考える際には、
「提供する商品やサービスの詳細」「競合他社との違い(差別化ポイント)」「提供する価値や解決する課題」といった内容をもとに
考えていきます。
例えば、アパレル関連事業を計画している場合、以下のように具体化できるでしょう。
「提供する商品やサービスの詳細」 →主に20代女性向けのカジュアルウェアを扱い、オンライン販売を中心に展開。
「競合他社との違い(差別化ポイント)」→特に、パーソナライズされたコーディネート提案や定期購買型のサービスを導入。
「提供する価値や解決する課題」→おしゃれを楽しみたいが忙しくて買い物に時間を割けない層に向けて、トレンド感と手軽さを両立
した商品づくりを行う。
このように、具体的な内容を組み込むことで、事業の方向性が明確になります。
2.2会社名(商号)、所在地、役員、資本金の決定
●会社名(商号)の決定
会社名は、事業の顔となります。
「覚えやすさ」「業種や事業内容を反映」「使用可能かの確認」というポイントをおさえて決定しましょう。
たとえば、アパレル事業なら「トレンドブリッジ株式会社」という会社名が考えられます。
シンプルで発音しやすく、親しみやすい名前で覚えやすいでしょう。
また、ファッション業界での「トレンド(流行)」と、顧客やデザインの「ブリッジ(架け橋)」となるイメージを反映しています。
そして、商号や商標が他社と重複しないよう、「トレンドブリッジ」を法務局や特許庁で事前に確認しましょう。
さらに「株式会社」を付加して法的に問題がないかも調査します。
●所在地の選定
本店所在地は、登記に必要な情報です。
「顧客や取引先へのアクセスが良い立地」「オフィスコストや固定費を抑えられる場所」「事業活動に必要なインフラが整っている地
域」というポイントをおさえて決定しましょう。
小規模事業では、自宅を所在地として利用する場合もあります。
●役員の選任
会社設立には、取締役や代表取締役などの役員を選任する必要があります。
役員の人数は会社の規模や事業内容によりますが、信頼できるパートナーを選ぶことが重要です。
株式会社では、取締役会を設置しない場合でも最低1名の取締役が必要です。
●資本金の決定
資本金は会社運営の基本資金であり、事業規模や信頼性にも影響します。
「設立時の必要経費(オフィス費用、設備投資など)」「取引先や金融機関からの信頼を得るための適切な金額」
「株式会社の場合、(1円からでも設立できるものの)実情に合わせた金額設定」というポイントをおさえて決定しましょう。
例えば、スタートアップ企業では300万円~500万円程度を資本金とするケースが一般的です。
3ステップ2:定款の作成と認証
3.1定款に記載すべき内容
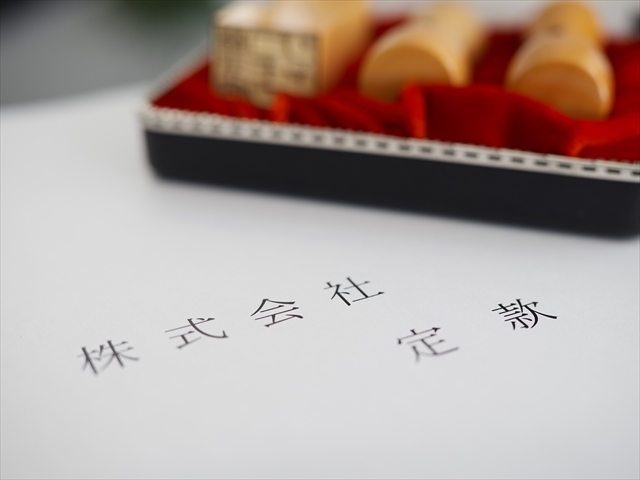
●絶対的記載内容(必ず記載が必要な事項)
以下の内容は、記載が欠けていると定款自体が無効となります。
「目的」→会社が営む事業の内容を具体的に記載します。例えば、「衣料品の製造および販売」「アパレル商品の輸出入事業」など。
「商号」→会社名(商号)を記載します。
「本店所在地」→会社の本店所在地を記載します。通常は市区町村までの記載で問題ありません。
「設立時の出資額(資本金)」→会社設立時に払い込まれる資本金の額を記載します。
「発行可能株式総数(株式会社の場合)」→会社が将来的に発行可能な株式の総数を記載します。
●相対的記載内容(記載しなくてもよいが、記載することで効力が生じる事項)
「株式譲渡制限」→株式の譲渡に制限を設ける場合に記載します。例えば、取締役会の承認を必要とする旨など。
「事業年度」→会社の決算期を明記します。
●任意的記載事項(記載することで)
「取締役会や監査役の設置に関する事項」→会社の意思決定や監査体制を明確化し、ガバナンスを強化するためのルールを定めます。
「利益配分に関するルール」→利益の配当方法や留保基準を明記することで、出資者間のトラブルを未然に防ぎます。
3.2公証役場での認証手続き
株式会社を設立する場合、作成した定款は公証役場で認証を受ける必要があります(合同会社の場合は認証は不要です)。
認証手続きは以下の流れで進めます。
①必要書類の準備
●作成した定款(紙の定款または電子定款)
●発起人(資本金出資者)全員の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
●現金約42,000円(定款謄本を3通受け取る場合は43,000円)
●公証役場へ出すCD−R(公証役場で電子定款データを入れてもらう用で、データなしのもの)
●公証役場に行く人の実印と身分証明書(運転免許証または顔写真つきのマイナンバーカード)
●【法人が発起人の場合】その法人の印鑑証明書、登記簿謄本、押印された株主名簿
②電話予約
公証役場に電話をかけ、公証役場に行く日を決めましょう。
認証日は公証人の都合によります。
③公証役場での認証手続き
予約した日に公証役場を訪問し、必要書類を提出します。
発起人または代理人が手続きに立ち会います。
公証人が定款の内容を確認し、問題がなければ認証が行われます。
④受け取り
認証完了後、定款2通、CD−R、申告受理および認証証明書を受け取ります。
定款は、1通は法務局に提出する用で、もう1通は自社で保管します。
CD−Rにも電子定款データが入ってますので、大切に保管しましょう。
4ステップ3:資本金の払い込み
4.1資本金払い込みの手順
①発起人名義の銀行口座を用意する
資本金は、発起人(株主)のいずれか一人の名義の銀行口座(既存の個人口座でOK)に払い込みます。
新口座を作る必要はありません。
会社設立前に法人名義の口座が作れないためです。
②資本金を入金する
発起人全員が資本金を払い込むため、決められた金額を用意して入金します。
複数の発起人がいる場合は、それぞれの出資額を事前に確認し、正確に分配します。
資本金の振込日付は法務局提出日の前でなければなりません。
また、定款に示した金額を正確に入金しましょう。
振込金額(資本金総額)と払込日が通帳記入されていればOKです。
元々の残高は関係なく、振込金額が資本金総額となる点に注意しましょう。
法務局では、誰が振り込んだかまでは審査せず、金額と日付だけをチェックします。
また、すでに通帳残高が資本金額を超えている場合、資本金額を一度出金してから資本金額を入金します。
この資本金は、登記が完了すれば出金し、事業のために使うことができます。
③払い込み証明書を作成する
払い込みが完了したら、「払込証明書」を作成します。
まず、「通帳表紙のコピー」「通帳表紙の裏の1~2ページ目のコピー」「通帳の振込のあるページのコピー」を準備しましょう。
※紙の通帳がないデジタル通帳の場合は、上記の情報にあたるページを印刷します。
次に、払い込んだ金額や発起人の情報を記載し、発起人代表が署名押印します。
この紙を一番上にして、後ろに「通帳表紙のコピー」「通帳表紙の裏の1~2ページ目のコピー」「通帳の振込のあるページのコピー」
を重ね、左辺の2か所をホチキスで留めます。
この払い込み証明書は、登記申請時に法務局へ提出します。
5ステップ4:設立登記手続き
5.1法務局への申請方法
設立登記は、会社の本店所在地を管轄する法務局で行います。
登手続きは以下の流れで進めます。
①必要書類や必要なものの準備
●株式会社設立登記申請書(必要事項を正確に記入し、各所の押印も済ませておきます)
●公証役場で受け取った定款謄本1通 ※CD−Rは自宅で保管します。
●ホチキス留めをして作った、払い込み証明書
●発起人決定書
●就任承諾書(代表取締役・取締役・監査役の人数分)
●役員全員の印鑑証明書1通ずつ(発行後3ヶ月以内のもの)
●印鑑(改印)届書(この用紙は法務局の窓口にもあります)
●別紙(会社情報が書かれた紙)
●会社の実印(必須ではないものの、間違いがあった場合にその場で訂正できるので便利です)
●現金15万円(法務局で購入する収入印紙代)
②登記したい日に法務局へいく
登記したい日に法務局の会社設立の窓口へ行きましょう。
予約は必要ありません。
法務局に提出した日が会社設立日になります。
③収入印紙を購入して貼付する
法務局内で収入印紙を購入し、株式会社設立登記申請書に貼付しましょう。
④書類を提出する
法務局の会社設立登記の窓口で必要書類を提出します。
5分ほどで完了し、受付票を受け取ります。
もし不備があれば後日法務局から電話連絡がきます。
法務局で受け取った受付票の登記完了予定日時まで連絡がなければ、無事に会社が設立されたことになります。
5.2必要書類と記入の注意点
「誤字脱字に注意」
会社名や所在地の記入に誤りがないよう確認します。
特に数字や住所のミスが多いため、再確認を徹底してください。
「押印の漏れに注意」
書類には代表者印や発起人の印が必要な箇所が複数あります。
押印漏れは即時不備となるため、慎重に確認しましょう。
「定款と一致させる」
登記申請書に記載する内容は、定款と矛盾しないよう統一します。
特に資本金や事業目的の記載は重要です。
「提出期限を守る」
会社設立日を定款で定めた場合、その日から2週間以内に登記申請を行う必要があります。
6ステップ5:設立後の官公署への届け出

①税務署への届け出
税務署には以下の書類を提出します。提出期限が設けられているため注意が必要です。
●法人設立届出書(提出期限は会社設立から2か月以内)
●青色申告承認申請書(提出期限は設立から3か月以内)
●給与支払事務所等の開設届出書(提出期限は設立から1か月以内)
●源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(提出は義務ではないものの、提出した方が有利です)
②都道府県税事務所への届け出
●法人設立届出書(提出期限は設立から1か月以内、東京23区の場合は15日以内)
③市町村役場の法人税務課
●法人設立届出書(提出期限は設立から1か月以内)
※東京23区内に設立の場合は、都税事務所に届出をすれば、区役所へ届ける必要はありません。
④日本年金機構
●健康保険・厚生年金保険新規適用届書(加入義務になってからできるだけ早く)
●健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届書(※雇用や給与形態による)
⑤労働基準監督署
●労働保険の保険関係成立届(従業員雇用後10日以内)
●労働保険概算保険料申告書(従業員雇用後10日以内)
⑥ハローワーク
●適用事業所設置届(従業員雇用後10日以内)
7おわりに
7.1営業開始に向けた準備(許認可取得、マーケティング活動など)
●許認可取得
事業内容によっては、営業開始前に特定の許認可が必要です。
許認可を取得せずに営業を開始すると、行政指導や罰則を受ける可能性があります。
以下にいくつかの例を挙げます。
「中古品販売」→警察署で「古物商許可」の申請が必要。
「輸出入業」→税関で「輸出入者コード」の登録が必要。
「飲食店営業」→保健所で「食品衛生責任者」資格の取得と営業許可が必要。
●マーケティング活動
顧客に自社のサービスや商品を認知してもらうため、効果的なマーケティング活動を行います。
営業開始初期は認知度が低い時期であるため、キャンペーンや特典を活用して顧客の関心を引きつける工夫をすると効果的です。
「ターゲット分析」→顧客層を明確化し、ニーズに合わせたアプローチを検討。
「広告・宣伝」→SNS、ウェブサイト、チラシなど、適切な媒体を選び、効果的に情報を発信。
「ブランド構築」→ロゴやキャッチコピーを通じて、自社のイメージを明確化し、顧客に訴求。
7.2専門家への相談のすすめ
会社設立後の運営は、法務、税務、人事労務、経営戦略など、専門的な知識を必要とする課題が数多く存在します。
これらの課題をすべて自分一人で対応しようとすると、時間や労力がかかるだけでなく、思わぬミスやトラブルを招くリスクもありま
す。
そのため、専門家のサポートを受け、事業運営をスムーズに進めることをおすすめします。
たとえば、司法書士や行政書士は、会社の登記手続きや許認可の取得をスムーズに進めるためのサポートを行います。
設立後に必要な変更登記や、新たな事業展開の際の許認可取得も、専門家に相談することで迅速に対応できます。
また、税理士は、税務申告や帳簿作成といった複雑な手続きを代行し、会社の節税対策や財務健全化をサポートしてくれます。
特に、設立後初めての決算期は税務手続きに慣れていないことも多いため、税理士の助けを借りることで余計な負担を軽減できます。
さらに、社会保険労務士は、労働保険や社会保険の手続きだけでなく、従業員を雇用する際の人事制度の整備や労務管理の改善につい
てもアドバイスをくれます。
適切な人事体制を整えることで、従業員とのトラブルを未然に防ぐことができます。
また、経営コンサルタントは、事業戦略やマーケティング戦略についての専門的なアドバイスを行い、市場競争力の強化や新規事業の
開拓を支援します。
専門家への相談を通じて得られるメリットは大きく、手続きの効率化や法的リスクの回避だけでなく、事業運営全体の効率化や安心感
の向上につながります。
こうしたサポートを適切に活用することで、会社設立後の不安を軽減し、より安心して事業に専念することができるでしょう。
7.3まとめ
いかがでしたか?
これから会社を設立し、事業を運営していくうえで大切なのは、計画性と柔軟な対応力です。
明確な目標を持ちながら、一歩一歩着実に進めることで、事業を成功に導くことができるでしょう。
この記事が、会社設立の一助となり、新たな挑戦を後押しするものとなれば幸いです。
この記事は中国輸入代行業者である中国仕入れのさくら代行が執筆しています。
中国仕入れのさくら代行 https://www.sakuradk2.com
さくら代行は日本と中国に拠点を持ち、事業者様の代わりに中国国内の全ての業務と日本への納品(FBA直送含む)を行うことを使命とし
ております。
中国輸入販売をお考えの方は是非さくら代行サービスをご利用くださいませ。